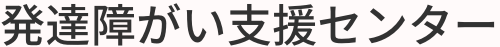こんにちは、
発達障がい支援センターの真鍋良得です。
「もしかして、自分は発達障害かもしれない…」
そんなふうに感じたとき、不安や混乱、孤独を感じることもあるかもしれません。
でも、まずは深呼吸して、少しずつ理解を深めていきましょう。
このブログでは、発達障害の診断を受ける前に知っておきたい大切なことをお伝えします。
1. 「発達障害かもしれない」と思うのは悪いことじゃない
まず最初にお伝えしたいのは、「もしかして」と思う気づきは、自分をよりよく知ろうとする前向きな一歩だということ。
社会での生きづらさ、人間関係の難しさ、仕事でのつまずき。
そうした日々の中で、「なんで自分はこんなに疲れるんだろう」と悩んできた方も多いはずです。
それに名前がつくこと、つまり「発達障害」という可能性を知ることは、決して恥ずかしいことではありません。
2. 発達障害ってそもそも何?
発達障害とは、生まれつき脳の働きに特性がある状態のことをいいます。
よく知られているのは以下のようなものです。
- 自閉スペクトラム症(ASD):対人関係やコミュニケーションが苦手。こだわりが強いなど。
- 注意欠如・多動症(ADHD):集中力が続かない、落ち着きがない、忘れ物が多いなど。
- 学習障害(LD):読み書きや計算に特定の困難がある。
どれも「性格のせい」ではなく、脳の仕組みの違いからくるもの。
特性が強く出ていると、日常生活に困りごとが生じることがあります。
3. 診断を受けるときに大切な「心理検査」のこと
発達障害の診断を正しく行うには、心理検査がとても大切です。
心理検査では、知能のバランスや認知の傾向、社会性などを専門的に評価します。
これによって、単なる「思い込み」や「一時的なストレス」の影響ではなく、その人の特性を客観的に把握することができます。
最近では、心理検査によらない方法で診断を下すケースもあるようですが、適正な診断のためには、心理検査の結果を踏まえた多面的な評価が必要です。
検査結果は、医師がより正確な判断を下すための大切な材料になります。
診断を受ける際は、「心理検査をきちんと行ってくれる機関かどうか」も確認しておくと安心です。
4. 診断を受けるメリットとデメリット
メリット
- 自分の特性を客観的に知ることができる
- 必要な支援や配慮を受けやすくなる(職場や学校など)
- 適切なサポートや治療につながる
デメリット
- 診断名がつくことで、ショックを受ける場合もある
- 周囲の理解が得られないこともある
- 医師によって見解が異なることもある
診断は「ラベル」ではなく、「地図」だと考えてみてください。
これまでの生きづらさの理由がわかり、これからの道を考えるヒントになります。